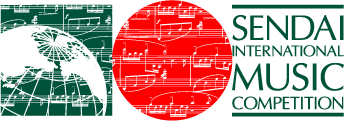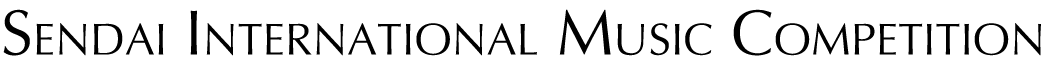コラム&レビュー
第7回コンクール評②
第7回仙台国際音楽コンクールピアノ部門を聴いて
音楽評論家:萩谷 由喜子
現在、国際音楽コンクール世界連盟に加盟しているピアノの国際コンクールで日本を開催地とするのは、浜松、高松、そして仙台の3コンクールだ。うち、仙台には他の2者にみられない特色がある。いや、世界的に他の国際ピアノコンクールを見渡してもおそらく見いだせないその大きな特色とは、セミファイナル時点から常設プロオーケストラと共演して協奏曲を演奏することと、ファイナルでは、いわゆるマスターピースの協奏曲1曲に加え、基礎力の問われるモーツァルトの中でも演奏機会の少ない協奏曲1曲が課されている点である。つまり、本審査に臨む者は全部で3曲の協奏曲準備が必要となる。その特色を苛酷な課題と受け止めるか、願ってもない僥倖ととるか、コンテスタントの意識はいかがであろうか?
すると、入賞者記者会見では皆、異口同音に、応募の動機として「3曲もの協奏曲を弾かせていただけること」を挙げ、「結果以上に、3曲の協奏曲体験をできたことが嬉しかった」と述べるのをきき、そのモチベーションの高さが彼らに入賞をもたらしたのだと痛感した。
実際、すでにプロとして活動している世のピアニストでも協奏曲の演奏機会に恵まれるのは一握りの者にすぎず、皆、その機会到来を鶴首している状況を思えば、これは本当に若い演奏家の卵たちへの何物にも替え難い福音だ。こんな贅沢が可能なのも、同コンクールが仙台フィルハーモニー管弦楽団という優秀なホスト・オーケストラを有しているからだ。また逆に、仙台フィルの側からいえば、3年に1度のこの大役が同フィルの重要な実力養成の場となるとともに、大切な経済基盤となっているときく。コンクールとオーケストラの絶妙な協調関係。それが、若い演奏家たちのまたとない勉強機会を提供しているのだから、理想的といってよい環境ではなかろうか。ぜひ、継続して欲しい。
もうひとつ、見逃せないのは、指揮者の力量である。今回、広上淳一マエストロという、きめ細やかにソリストの意を汲んでそれを実現させながら、巧みにオーケストラをドライヴして瑞々しい演奏を生み出す、卓越した指揮者を得たことにより、ソリスト、オーケストラ、聴衆の三者にとって幸せな音楽が紡がれたことを特筆しておきたい。
さて、入賞者6名について振り返ってみよう。ベートーヴェンがセミファイナル、モーツァルトとマスターピースがファイナルである。
第6位のキム・ジュンヒョンは、ベートーヴェンの第4番ト長調、モーツァルトのヘ長調K459、チャイコフスキーを弾いた。表現意欲が旺盛で、無難に弾くのではなく、自分らしいカラーを出すべく、テンポも充分に操作し、激しい部分はエネルギーたっぷりに力感を込めて弾いた。前向きなチャレンジ精神を評価したい。
第5位の平間今日志郎は今年21歳の若手だが、音楽が成熟していた。ベートーヴェンの第3番ハ短調、モーツァルトの変ロ長調K450、及びラフマニノフの第2番ハ短調を弾いたが、どの作品に対しても表現の方向性が明快である。ラフマニノフはオーケストラとの合わせが成功していたので、あとでその点をきくと、別の機会が一度あったとのことだった。
第4位の佐藤元洋は、他の入賞者5名がスタインウェイを選択した中、彼のみカワイの「Shigeru Kawai」を選んで、そのブリリアントな音色にリリックな歌心をのせて繊細な音楽を聴かせてくれた。ベートーヴェンは第3番ハ短調、モーツァルトはト長調K453を選び、マスターピースはやや珍しいリストの第2番イ長調だった。今回、ファイナルの任意曲では6名中4名がチャイコフスキーを弾く中、せっかく余人の弾かないリストを選んだ以上、さらに一歩踏み込んだリスト像を彫琢出来ていたなら、美音という武器があるのだから、もう少し順位が繰り上がっていただろう。
第3位は28歳のロシア人女性ダリア・パルホーメンコ。女性の参加者がコンクール出場者37名中7名と少数で、ファイナルに進出したのは彼女1人であったが、女性を代表するかのように、馥郁とした鳴りのよい音で、ベートーヴェンの第4番ト長調、モーツァルトのト長調K453、そしてチャイコフスキーを聴き応えたっぷりに弾いてくれた。
第2位のバロン・フェンウィクは25歳のアメリカ青年。ベートーヴェンの第3番ハ短調、モーツァルトのト長調K453、チャイコフスキーを弾いた。会見で明かしてくれたのは、少年時代からヴァン・クライバーンに憧れて、クライバーンのチャイコフスキー・コンクール優勝時のCDを擦り切れるほど聴き、自分もいつか…と誓ってきたというエピソード。アメリカン・ドリームがここ仙台で新たなアメリカン・ドリームの花を開かせた。
最後に、優勝者のチェ・ヒョンロクについて。今年26歳になるこの韓国の若者は、ベートーヴェンの第4番ト長調、モーツァルトのト長調K453、そしてチャイコフスキーの3曲をすべてムラのない高水準で聴かせた。文句なしに最も高いテクニックと安定感を兼ね備えていたので、審査も紛糾しなかったようだ。ただし、本人に、3曲のうちどれが一番成功したか尋ねたところ、恥ずかしそうに「どれも全然だめです」と答えた。そこに向上心と伸びしろを感じ、頼もしく思えた。
ともあれ、納得のいく結果であり、よいコンクールであった。