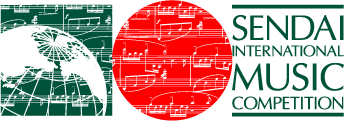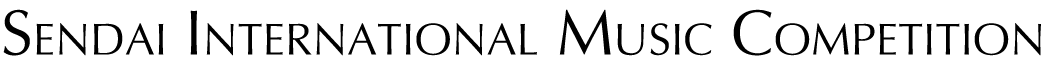コラム&レビュー
第7回仙台国際音楽コンクール
ピアノ部門課題曲の特質
音楽評論家:萩谷 由喜子
2001年に創設された仙台国際音楽コンクールは3年周期でこれまでに6回開催され、多く逸材を世に送ってきた。2019年にはその第7回を迎える。同コンクールの最大の特色は、協奏曲重視型であることだ。通常の国際音楽コンクールの場合、協奏曲が課されるのはファイナルのみだが、同コンクールではセミファイナルから協奏曲が課題とされる。しかもファイナルでは、2群の選択範囲から各1曲、計2曲を弾くことになる。つまり、出場者は協奏曲を3曲用意しなければならないわけだが、見方を変えれば、ファイナルまで勝ち残ることができれば、プロオーケストラと3曲もの協奏曲共演を体験できるのだ。
プロの演奏家にとって、独奏と協奏曲は2本柱だ。しかし実際には、ごく少数のスター・ピアニストを除いて後者の機会は滅多になく、機会がないがゆえに腕もあがらず、従ってオファーもこないという悪循環となりがちだ。そうならないために、コンクール挑戦時代から1回でも多くの協奏曲演奏機会を与えようというのが、同コンクールの狙いなのである。2019年の第7回でもこのスタイルが踏襲される。では、ピアノ部門各審査段階の具体的な課題曲をみていこう。
予選では30~40分のリサイタルプログラムが求められる。曲目は任意だが、J.S.バッハ、ハイドン、モーツァルト、ベートーヴェン、シューベルト、メンデルスゾーン、ショパン、シューマン、ブラームスの作品から1曲以上かつ、10分以上の演奏を含むこと、とされる。この課題の意図は、選曲のバランスと全体のコンセプトをみることと、J.S.バッハからブラームスに至るドイツの鍵盤音楽、及び、古今最大のピアノ音楽作曲家ショパンという、ピアニストを志す者の根幹をなすレパートリーをどれほど身に着けているかを問うところにある。ソナタの場合は全楽章が課されているというのも、小品とはおのずと異なる構築力をみることができるからだ。このような核となる大曲に小品やエチュードなどをいかに取り合わせるかで、リサイタリストとしてのセンスがはっきりとわかる。
セミファイナルの課題は、前回と同じく、ベートーヴェンのピアノ協奏曲 第3番 ハ短調、または、ピアノ協奏曲 第4番 ト長調のどちらかを弾くこととされた。記者会見で野島稔審査委員長が「ベートーヴェンの3番と4番はキャラクターが全く異なる、一つの宇宙の両極ともはらんでいるということで、たとえそのピアニストが将来どういう演奏家を目指すにしても、まずこの曲のどちらかをよく弾けなければいけないという発想から、このように決めました。」と語ったように、対照的な性格の2曲はベートーヴェンの二つの顔を体現するため、ピアニストたる者、少なくとも、いずれかを完全に手中に収めていなければ話にならない。
1803年に完成し同年4月5日、ベートーヴェン自身の独奏により初演された第3番は彼の全協奏曲中、唯一の短調作品だが暗さや悲痛さは感じられず、情熱に溢れ、雄渾で逞しい。モーツァルトの協奏曲K491と同じ調性で書かれ、冒頭句もK491を彷彿とさせるところから、モーツァルトへのオマージュも感じられる傑作だ。
一方、第4番は1806年に完成、翌1807年3月の私的初演を経て、1808年12月22日にやはり本人によって公開初演された。当時の彼は耳の病が深刻化していたため、残念ながら、不本意な演奏であったようだ。しかし、のちに第三者によって盛んに演奏されるようになり、現在では第5番の先駆作として極めて高い評価を受けている。冒頭5小節にピアノ独奏楽句が置かれてからオーケストラが入ってくる、という斬新な手法は第5番をあきらかに先触れする。曲は気品に満ち、明るく高雅な雰囲気を持つ。
そしてファイナルでは、モーツァルトの5曲から1曲を選ぶ課題と、古典派から近代までの名作協奏曲16曲の中から任意の1曲を選ぶ課題が出されている。
一般に、モーツァルトのピアノ協奏曲というと、1785年のK466 ニ短調~1791年の最終作K595 変ロ長調までの8曲の演奏機会が多いが、これら珠玉の後期8作は突如生まれたわけではなく、そこに至る過程がある。選択範囲の5作はいずれも1784年に書かれたもので、後期傑作群を予告する隠れ重要作である。にもかかわらず、プロでさえもこれらを勉強した人は多くない。それを敢えて問うことで、資質をみるとともに若手に勉強機会を与えることが意図されている。
筆者は前回の第6回も拝聴したが、ファイナリスト全員が、あたかも学内試験のような初々しい緊張感をもってモーツァルトを弾いたことを今もありありと思い出す。というのも、著名大曲の勉強に追われてか、これらにまでは手が回らず、ほぼ全員がコンクールに参加したおかげで取り組む機会を得たそうであった。
そして、もうひとつの課題は、1809年完成11年初演のベートーヴェンの『皇帝』から1921年完成22年初演のプロコフィエフの3番まで、およそ1世紀と10年の間に成立した、古典派から近代までの16曲のうちから、いずれか1曲を弾くというものだ。
ピアノとオーケストラの協奏性の高い『皇帝』、ポーランドの民族情緒がピアノに見事に結実したショパンの2曲、実験精神旺盛なリストの2曲、名人芸追披瀝の対極にあるがゆえの難曲シューマン、いずれも交響曲にも匹敵する重量級大作ながら性格の対照的なブラームスの2曲、型破りでロシア的民族色の濃厚なチャイコフスキー、20世紀に書かれながら19世紀的ロマンの残照に輝くラフマニノフの3曲、洗練に溢れジャズの香りも漂うラヴェル、バルトーク晩年の透徹した境地の反映された第3番、モダニズム志向が強くソロには超絶技巧が求められるプロコフィエフの第2番、彼ならではの創意がさらに大きく開花した20世紀ピアノ協奏曲屈指の傑作、第3番。すべて後世に残った名作だ。どれを選ぶにせよ、その作品の本質を掬い取れるか否かが問われることになろう。
野島稔審査委員長の「この課題曲の構成は、ほぼ理想的ではないかと自負しております。限られた日数、時間の中でひとりの出場者がどういう音楽家なのか、どういうピアニストなのかを見極めるために必要なものが、判断の材料としてこの上なくまとまっていると考えています。」との言葉からもわかるように、選び抜かれ考え抜かれた「仙台の課題曲」である。若者たちの渾身の挑戦を期待したい。
《この文章は仙台国際音楽コンクールニュースレター2018年2月号に掲載されたものです》