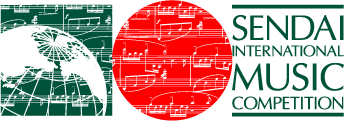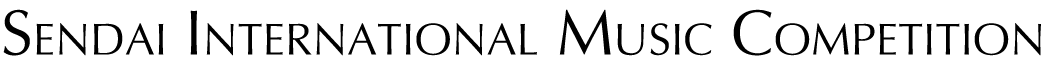コラム&レビュー
第7回コンクール評④
音楽評論家:沼野 雄司
「モーツァルトは難しい」という凡庸な表現がある。大抵は、シンプルなだけにかえって奏者の欠点が見えやすいという意味で用いられるわけだが、今回感じたのはそれとは異なった意味でモーツァルトは難しいということだった。単に技術的に、十分難しいのだ。プロの演奏ばかりに接しているとあまり気づかないけれども、コンテスタントらの奮闘に接し、改めて楽譜を眺めてみると、つくづく難しい。そしてもちろんブラームスもメンデルスゾーンも同様。これは不可能では?という箇所がいくつもある。普段、「コンクール」を聴くことがほとんどない身にとっては、この難しさを実感したことがまずは収穫だった。
以下、ファイナルの演奏について、6位から順に私見を述べるが、その前に高関健の指揮について触れておかねばならない。それぞれに癖があるコンテスタントの演奏にぴたりとつけ、心持ち音量を抑えながらも、しかし音楽として十分に聴かせるというのは並大抵の技ではない。コンクール期間を通して、いたく感服した次第。
6位となった荒井里桜のモーツァルト(K219)は、まずはヴィブラートの多さが気になった。そして「トルコ風」の部分で、もう少し音色や表現の変化があればとも。ブラームスも、ヴィブラートがかなり深いのに加えて、ノイジーな音とふくらみのある美音の交替がややデジタルに感じられてしまう。時に響かせる凄みのある高音には、思わず惹き込まれてしまう魅力があるのだが。
同じく6位のコー・ドンフィのモーツァルト(K219)には、強い意志が漲(みなぎ)っている。第2楽章の濃厚な表現など、思わずほだされてしまう瞬間もあったのだが、しかし全体としては力むあまりに、単調さが前面に出てしまった。シベリウスの協奏曲でも、熱量は相当であるものの、冒頭のモノローグの途中から早くもガリガリとした響きの世界に入ってしまうのは、いささかやり過ぎのように思われた。
5位のイリアス・ダビッド・モンカドはまだ十代ながらも、個性的な演奏。モーツァルト(K216)は素晴らしかった。昨今の主流といってよい、ピリオドとモダンのハイブリッドな様式を自然に身につけており、重音などではほれぼれするくらい純正な音程を響かせる一方で、要所ではきりっとしたヴィブラートを効かせる。筆者の採点ではモーツァルトに関しては彼と北田が最高点だった。しかしチャイコフスキーは、あまりに室内楽的な表現に終始したのに加えて(それはそれで持ち味という気もしたが)、速いパッセージで慌てすぎてしまったのが惜しまれる。
4位の北田千尋のモーツァルト(K219)には驚愕。音に柔らかくも確固たる芯があり、何より一瞬一瞬に新鮮な表情がある。とりわけ第2楽章は類例がない美しさ。そして、同じく息を呑んだのがメンデルスゾーンの協奏曲。最初のフレーズから細かい抑揚があり、常に人の呼吸が感じられる。時として音程に危うさを感じさせることもあったが、細かいヴィブラートの選択や制御が的確で、完成度は極めて高い。少なくともファイナルの2曲のみを見た場合、筆者は北田がもっともすぐれていたように感じた(これについては後述)。
3位の友滝真由のモーツァルト(K219)は、伸びのある高音が美点。ただ、最後まで聴いていると、音の延ばし方、歌い方が一本調子なのが気になってくる。一方、ブラームスは、パワフルな音量による豪快な熱演。強引な部分も目につくが、しかし曲のスケールを考えると、こうした演奏は十分に理がある。実際、ファイナル全体を通じて、このブラームスがもっとも観客を沸かせた。
最高位(第2位)となったシャノン・リーのモーツァルト(K218)は、まろやかな響きを一貫して保持した演奏。大過なく進んでゆくものの、表現としての引っかかりには欠ける(彼女の場合、K219を選んだ方がよかったように思う)。一方のチャイコフスキーは、旋律を存分に歌わせてとてもチャーミング。細かい音型に愛くるしい表情があり、先の展開が常に楽しみだった。テンポは随所で崩れそうになったものの、高関の好サポートが生きて、致命傷にはならずに済んだ。
さて、ファイナルのみを聴いた筆者は、北田、リー、友滝という順位を勝手につけていた。結局、蓋を開けてみればリーが最高位であったわけだが、多くの審査委員が述べていたのは、セミファイナルで彼女が弾いたバルトークの素晴らしさ。実際、運営委員長が曲目を指定する入賞者ガラコンサートにおいて、リーはバルトークを、そして次点の友滝もセミファイナルのプロコフィエフを演奏した。つまり、この二人に関してはファイナル以前の演奏が高く評価されたと想像されるのである。なるほど確かにこうしたコンクールというのは、一次、二次と積み重ねていった結果として考えるべきなのだろう。
コンクール全体を通して、常にオーケストラがフル稼働し続けるという贅沢さに加えて(仙台フィルの熱気あふれるサポート!)、様々な点できめ細やかに運営がなされていたのは感心するばかりで、この点、関係者には満腔の敬意を表したい。ただ、小さなことをひとつだけ。授賞式において「杜の都親善大使」の女性二人が、常に正面でポーズをつけて立っているのは、時代錯誤に感じられるとともに国際コンクールとしての品位を損ないかねないように思う。この点だけはご一考をおすすめする。