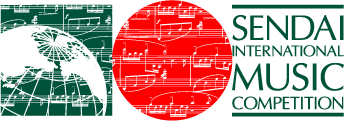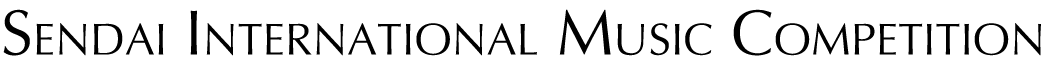コラム&レビュー
第7回コンクール評③
音楽評論家:松本 學
第7回仙台国際コンクールヴァイオリン部門が、2019年6月15〜30日の日程で開催された。従来の5月スタートではなく、初めてピアノ部門を先行させた上で6月開催としたのは、今年がいつにないコンクール・ラッシュとなったためである。例年仙台と時期が重なるモントリオール(今年は5/29-6/5)に加え、今回はエリーザベト(ベルギー 4/29-5/25)やマイケル・ヒル(ニュージーランド 5/31-6/8)、レオポルト・モーツァルト(アウクスブルク 6/1-7)などの国際コンクールが一斉に並んだためにとられた措置だ。さらにそのような事前対策にもかかわらず、昨年末になってチャイコフスキーが完全に被るスケジュール(6/17-27)を当ててきたのは残念だった。結果、仙台に限らず、それぞれにコンクール常連出場者の面々が分散してしまったのはコンクールにとって好ましいことではないし、コンテスタントたちもエントリーできる可能性が減るので嬉しくはないはずだ。
そのような難しい状況の中でも、仙台は独自の視点とアイディアにより、オリジナルのカラーを発揮していたことは間違いない。コンチェルト・コンクールというアイデンティティはそのままに、例えば、課題曲の設定にも斬新さが込められていた。特に今回目を引いたのは、何と言ってもセミファイナルである。コンチェルトを弾いた後に、コンサートマスター席に座って、ブラームスとシュトラウスのソロを弾くというのは、一連の流れに一抹の違和感は残ったものの相当にユニークであった。同じコンテスタントにも関わらず協奏曲とコンマスとではオケとの対話の様子が随分と異なり、特に後者ではコンテスタントによってオケの音が大きく変化するのは改めて興味深かった。いずれにせよ命運を分かつのは、コンチェルトであろうとコンマスであろうと自らのパートだけではなく、スコアを細部まで体に染み込ませているかどうかということになる。
さて、ファイナリスト6名の演奏をざっと振り返っておく。
エリーザベト4位に輝いた後に仙台を選んだシャノン・リーは、モーツァルトでは最初の1音で線の細さや金属的なサウンドを感じさせたが、しばらくすると落ち着き、安定感高く演奏。後半に向かって愉悦感も漂い、モーツァルトらしさを聴かせた。この作曲家には徹底した精度や様式感、クリーンな音などと併せて、生命感、愉悦感が必須であり、それゆえに難しい。半分のファイナリストがこのモーツァルトで苦戦した様子を目の当たりにし、予選やセミファイナルでなく、ファイナルの課題曲にこの作曲家を持ってくるというのは、なんとも酷なことだと思わずにいられなかった。リーが選んだコンチェルトはエリーザベトでも弾いたチャイコフスキー。丁寧に歌い込み、音も美しかったが、オーケストラとの息がわずかに合わなかったのが惜しまれる。
今回が2度目の仙台へのチャレンジとなる友滝真由はきわめて折り目正しい音楽造り。どの弦もどの音域も美しく鳴らし、そのためモーツァルトは純度が高い。フィナーレ中間部でわずかに乱れたが大きな問題でなく、より躍動感があればさらに高評価を得ただろう。ブラームスでは第1楽章がいささか不安定だったが、第2楽章からは落ち着き、オーソドックスにまとめた。スケールの大きさが望まれる。
北田千尋はメンデルスゾーンでは力みがなく、しかし音量は十分。第1楽章の後半で少しだけもつれたものの、全体としてはお手本のように整えられた演奏を聴かせた。反面、ゆったり目のテンポで、やや丁寧に進めすぎた感もあり、求心力にはいささか物足りない。
最年少参加のイリアス・ダビッド・モンカドは、モーツァルトは端正で好印象。チャイコフスキーの第1楽章カデンツァ直前で肩当てを落としたのにはヒヤリとさせられたが、むしろそこからが音も充実し、集中力と気迫のこもった素晴らしい演奏となった。
荒井里桜は初の国際コンクールへのチャレンジでナーバスになったのか、終始ピッチが安定せず、モーツァルトではフィナーレの中間部アレグロに入っても、音楽のキャラクターがあまり変化せず、平坦に終わってしまったのが残念だった。ブラームスでもその不安定さは解消できなかった。才能のある方なので、これからの成長を期待したい。
コー・ドンフィはそのチャレンジングでリスクを恐れない強烈な表現意欲は高く買うが、扇情的とも言える濃厚なアゴーギクやデュナーミクは、結果として力みの連続となりフレージングもピッチも崩れ、何より音が潰れてしまうのは聴いていて正直辛いものがあった。テクニック自体はあり、人を惹きつける力もあるので、スタイルを再考すべきだろう。
セミファイナルの各日から選ばれる聴衆賞は、1日目が古澤香理、2日目がシャノン・リー、3日目からはアンドレア・オビソの3名。この中からオビソについて触れておきたい。一昨年のミュンヘンARD国際コンクールのファイナルでも彼のプロコフィエフ第1協奏曲を聴いたが、当時よりもさらに作品を手の内にし、きわめてアグレッシヴにオーケストラと刺激的なセッションを繰り広げた様子は、聴衆の共感を得るに十分だった。共演した仙台フィル・メンバーの多くも、彼とのジャムセッション張りの丁々発止としたやりとりを楽しんだようで、この若きイタリア人を強く推していた。しかしながら、指揮者を飛び越えて、自らが直接オーケストラを引っ張り、コントロールしようとした姿は審査委員の評価を得られず、このコンクールの評価の指針のひとつを示す典型的な例となった。
その他では、モーツァルトではカデンツァやアインガングに各自の個性が出ていたので、作曲者などの詳細なデータを公開するとなおよかったと思う(規定には「通過者に連絡」とのみ記載)。また、コンテスタントが望むセミファイナルのフィードバック・セッションの再検討などは課題のひとつと言える。
広報的には、これまできわめて勤勉に展開してきたボランティア・ブログに加え、ようやくSNSを利用するようになったことは仙台を超えた全国の音楽ファンへのアピールに効果的だと思う。