コラム&レビュー
シャノン・リー(第7回ヴァイオリン部⾨最⾼位[第2位])東京交響楽団 名曲全集 第152回 演奏レポート
2019年12⽉14⽇
演奏曲⽬/ブルッフ︓ヴァイオリン協奏曲 第1番 ト短調 作品26
会場/ミューザ川崎シンフォニーホール
音楽評論家:松本 學
第7回仙台国際⾳楽コンクールで最⾼位を得てから半年を経た2019年12⽉、シャノン・リーが東京交響楽団との共演のために再び⽇本に戻ってきた。コンクールからさほど時も経っておらず、さらにセミファイナルのバルトークとファイナルのモーツァルトを収めた受賞記念ライヴCD(とブラームス第2ソナタが⼊ったエリーザベト王妃国際⾳楽コンクール・ライヴCD)もリリースされて程なかったこともあり、彼⼥の演奏についてはイメージが薄れてはいなかったものの、それでもこの半年という期間での彼⼥の成⻑や、コンクールの課題曲でなかったブルッフのヴァイオリン協奏曲第1番が聴けることに期待が⾼まったのは⾔うまでもない。
結論から⾔えば、彼⼥の演奏は満⾜のいくものだった。リーによれば、ブルッフのこの協奏曲は最初期に学んだコンチェルトのひとつで、かなり久し振りに取り上げるとのことだったが、その分フレッシュな感性が横溢する聴き応えのある仕上がりとなった。もとよりテクニックの⾼さは仙台で⽬の当たりにしていたし、それ以外でもエリーザベト王妃コンクールやハイフェッツ⾳楽祭の記録映像などから⼗分にうかがい知れる。
全体としては、リーのアプローチは、慣習的なスタイルに基づいたもので、例えば楽譜上は f とされている第1楽章〈前奏曲〉冒頭の独奏の⼊りは、息を潜めるような繊細な弱⾳で開始する。あるいは、同じく第1楽章の後半で独奏ヴァイオリンが半⾳階上⾏スケールの後に分散和⾳を連続させながらクレッシェンドしてゆく場⾯があるが、その最後の部分でオーケストラに付された p に合わせて⾳量を落とすところなどがわかりやすい例だ(クリスティアン・フェラスを例外とし、特に前者はほとんどのヴァイオリニストがそのように演奏する)。また、素直で健康的、⾃然な⾳楽作りは、リー⾃⾝の素直な⼈柄がそのまま表れたようでとても好感が持てる。⾳も美しく磨かれ、E線のハイトーンはつややかで輝かしく、G線の太い低⾳も深さ、逞しさ、愁いなど表情豊か。と同時に、両端楽章のエネルギッシュさや、第2楽章の⽢美な抒情性といった⾳楽のキャラクターの描き分けは明確だ。テンポの⾯でもラプソディックな第1楽章ではフレーズの各所に記されたエスプレッシーヴォの部分を中⼼に緩急を付けたっぷりと歌いこみ、また第1、第3楽章のメカニカルな箇所ではきっちりとリズムをキープするなど、細かな配慮を⾒せている。こういった楽想を的確につかんでゆくところは、仙台のコンクールでモーツァルトとバルトーク、チャイコフスキーのキャラクターを⾃然に弾き分けたセンスのよさそのままだ。ヴィブラート、ポルタメントもよい塩梅で、ブルッフらしいロマンと爽やかさを丁寧に表現していた。リーの演奏について欲を⾔うならば、デュナーミク(強弱の差)に⼀層の幅を出すこと、ピッチ(⾳程)、特に重⾳のそれの精度を上げること、そして表現をより確信的なものへと深めること……これらが今後の課題と⾔えるだろう。
最後に、指揮の秋⼭和慶と東京交響楽団が素晴らしいサポートを聴かせたことも特筆しておきたい。「秋⼭さんは作品を熟知しており、オーケストラともすぐに分かり合えてとてもやりやすかった」と、リハーサル初⽇を終えた時点で彼⼥も語っていた。コンサートマスター⽔⾕晃率いる東響の個々の奏者の完成度の⾼さと、トゥッティのふくよかさ、ソロを盛り⽴てようという姿勢は実に感動的だった。次の3⽉の仙台フィル*との共演や6⽉のリサイタルも実に楽しみだ。
*シャノン・リーが出演を予定していた仙台フィルハーモニー管弦楽団第335回定期演奏会(2020年3月6日・7日)は中止となりました。
《このレビューは仙台国際音楽コンクールニュースレター2020年2月号に掲載されました》
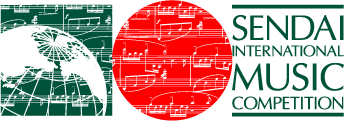
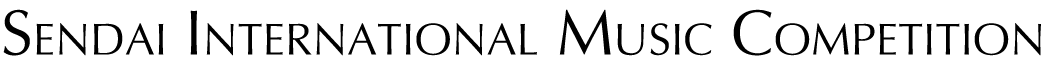
![シャノン・リー(第7回ヴァイオリン部⾨最⾼位[第2位])東京交響楽団 名曲全集 第152回 演奏レポート | 仙台国際音楽コンクール公式サイト](https://simc.jp/the7th/wp-content/themes/simc_jp_the7th/img/official/column.jpg)